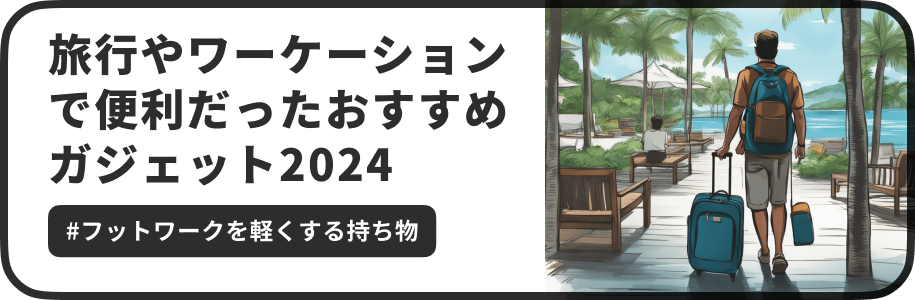デザインにおける同期・非同期による意思決定の使い分けについて
デジタルプロダクトデザインの現場では、デザインの意思決定をどのように行うかが、プロジェクトの進行と最終的な成果物の質を大きく左右します。意思決定の方法は多岐にわたりますが、大きく「同期的な意思決定」と「非同期的な意思決定」の2つに分類することができます。
同期的な意思決定とは、メンバーが同じ時間、同じ場所に集まり、リアルタイムで議論や作業を行いながら意思決定を進める方法です。例えば、「モブデザイン」と呼ばれる手法は、まさに同期的な意思決定の代表例と言えるでしょう。
一方、非同期的な意思決定とは、時間や場所を共有せずに、各自が都合の良いタイミングで意見やフィードバックを交換し、意思決定を進める方法です。Slackなどのチャットツールを活用したスレッドでの議論は、非同期的な意思決定の典型的な例です。
この記事では、これらの同期的な意思決定と非同期的な意思決定について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして具体的な使い分け方について解説していきます。
この記事のターゲット
デジタルプロダクトデザインを始めたばかりの初学者
同期的なデザイン意思決定と非同期的な意思決定の違いを知りたい人
それぞれの意思決定プロセスのメリット・デメリット、具体的な使い分け方を学びたい人
1. 同期的な意思決定(例:モブデザイン)
定義と特徴
同期的な意思決定とは、デザインチームのメンバーが同じ時間、同じ場所に集まり、リアルタイムで協力してデザインの意思決定を行うプロセスです。モブデザインは、同期的な意思決定の代表的な手法の一つです。モブデザインでは、通常、以下の役割を持つメンバーが同じ部屋に集まり、共同でデザインに取り組みます。
ドライバー:
手を動かしてデザインツールを操作する人
ファシリテーター:
デザインの方向性を示唆したり、ドライバーの操作を指示する人
オブザーバー:
デザインプロセスを観察し、意見やフィードバックを提供する人
多くの場合はデザイナーがドライバーやファシリテーターをすることが多いですが、PMやエンジニアなど開発状況に合わせて適切なメンバーが役割を交代できます。
モブデザインのセッションでは、全員が同じ画面を見ながら、口頭でのコミュニケーションを密に取り合い、リアルタイムでフィードバックを交換しながらデザインを進めていきます。短い時間で集中的に議論とデザイン作業を行うため、迅速な意思決定が可能です。
同期的な意思決定のメリット
迅速な意思決定:
リアルタイムで議論が進むため、意思決定までの時間が短縮されます。特に、時間制約があるプロジェクトや、スピーディーな意思決定が求められる場合に有効です。
高い解像度での議論:
対面でのコミュニケーションにより、言葉だけでなく表情やジェスチャーも交えて、より深いレベルでの議論が可能です。ニュアンスが伝わりやすく、誤解も生じにくいです。
チームの一体感と連帯感の向上:
同じ場所に集まり、共同で目標に向かって取り組むことで、チームメンバー間の連帯感や一体感が向上しチームビルディングとしての効果も期待できます。
暗黙知の共有:
言葉では表現しにくいノウハウや経験(暗黙知)が、議論や作業を通じて自然とチーム全体に共有されます。例えば、デザインツールなどのあまり知られていないショートカットやテクニカルな操作など。
教育効果:
経験豊富なメンバーのデザインプロセスを目の当たりにすることで、若手デザイナーや経験の浅いメンバーは学びを深めることができます。特にモブデザインでは、ファシリテーターやドライバーの思考プロセスを参加者が直接的に学ぶことができます。
コンテキストの共有:
全員が同じ時間に同じ情報に触れるため、デザインに関するコンテキスト(背景情報や前提条件)をチーム全体で共有しやすくなります。
同期的な意思決定のデメリット
時間と場所の制約:
メンバー全員が同じ時間、同じ場所に集まる必要があるため、スケジュール調整が難しい場合があります。特に、リモートワークが中心のチームや、時差のあるメンバーがいる場合には、時間調整が大きな課題となります。
準備と会議室の確保:
同期的な意思決定を行うためには、事前の準備や会議室の確保が必要になります。特に、大規模なチームや複数部署のメンバーが集まる場合には、会議室の確保が難航する可能性もあります。
一部メンバーの発言力過多:
議論がリアルタイムで進むため、発言力のあるメンバーや、積極的に意見を主張するメンバーの声が大きくなりがちです。内向的なメンバーや経験の浅いメンバーの声が埋もれてしまう可能性があります。
集団浅慮のリスク:
チームの連帯感が強い場合や、リーダーの意見に同調しやすい雰囲気の場合、批判的な意見が出にくくなり、安易な結論に陥るリスクがあります。
中断と集中力の低下:
議論が白熱しすぎると、本来の目的から逸脱したり、長時間にわたる会議で集中力が低下する可能性があります。適切な時間管理とファシリテーションが重要になります。
記録の残しにくさ:
口頭でのコミュニケーションが中心となるため、議論の内容や意思決定の過程が記録として残りにくい場合があります。後から振り返ったり、経緯を説明する際に不便が生じる可能性があります。
2. 非同期的な意思決定(例:チャットツールのスレッド内議論)
定義と特徴
非同期的な意思決定とは、デザインチームのメンバーが時間や場所を共有せずに、各自が都合の良いタイミングで意見やフィードバックを交換し、意思決定を行うプロセスです。SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールを活用したスレッドでの議論は、非同期的な意思決定の代表的な例です。
Slackのスレッドでは、デザインに関する質問や提案を投稿し、他のメンバーは自分の都合の良いタイミングで返信します。テキストベースでのコミュニケーションが中心となり、必要に応じて画像や動画などの資料を共有することも可能です。時間や場所にとらわれずに議論を進めることができるため、柔軟な働き方に適しています。
非同期的な意思決定のメリット
時間と場所の柔軟性:
メンバーは自分の都合の良い時間に議論に参加できるため、タイムゾーンや勤務時間の違いを考慮する必要がありません。リモートワークや多様な働き方を推進するチームに適しています。
深い思考と質の高いアウトプット:
発言する前にじっくりと考え、文章を推敲する時間が確保できるため、より深く掘り下げた議論や、質の高いアウトプットが期待できます。
記録の蓄積と可視化:
議論の内容がテキストとして記録されるため、後から議論を振り返ったり、意思決定の経緯を確認したりすることが容易です。ナレッジマネジメントや、新メンバーへの情報共有にも役立ちます。
内向的なメンバーも参加しやすい:
発言のタイミングや方法が自由なため、会議などでの発言が苦手な内向的なメンバーも、自分のペースで議論に参加しやすくなります。多様な意見を取り込みやすい環境を作ることができます。
非同期的な情報共有:
議論に参加していないメンバーも、スレッドを遡って議論の内容を把握することができます。情報共有の透明性が高まります。
非同期的な意思決定のデメリット
意思決定に時間がかかる:
リアルタイムでの議論ではないため、意見の交換や合意形成に時間がかかります。特に、緊急性の高い意思決定には不向きです。
コンテキストのずれや誤解が生じやすい:
テキストベースのコミュニケーションが中心となるため、言葉のニュアンスが伝わりにくく、意図が正確に伝わらない場合があります。画像などを活用して、誤解を減らす工夫が必要です。
温度感や熱意が伝わりにくい:
テキストのみのコミュニケーションでは、相手の表情や声のトーンが分からず、感情や熱意が伝わりにくいため、モチベーション維持が難しい場合があります。
議論の拡散と脱線:
議論がテキストベースで継続的に行われるため、話題が拡散したり、脱線したりする可能性があります。定期的に議論をまとめたり、ファシリテーターが議論の方向性を調整するなどの工夫が必要です。
即時的なフィードバックが得られない:
質問や意見に対して、すぐに返信が来るとは限らないため、即時的なフィードバックが必要な場合には不便です。
放置や未読リスク:
スレッドが乱立したり、通知が多い環境では、重要な情報が埋もれてしまったり、未読のまま放置されてしまう可能性があります。情報整理や通知設定の工夫が必要です。
3. 同期的な意思決定と非同期的な意思決定の使い分け
同期的な意思決定と非同期的な意思決定は、それぞれ特徴が異なるため、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。以下に、使い分けの指針となる具体的なケースと判断基準を示します。
使い分けの判断基準の比較表

具体的な使い分けケース
新規プロダクトのコンセプト検討:
初期段階(アイデア出し、コンセプトの方向性決定):
同期的な意思決定(ブレインストーミング、デザインワークショップなど)
コンセプト詳細化、仕様策定:
非同期的な意思決定(チャットスレッドでの議論、ドキュメントレビューなど)
UIデザインの詳細設計:
レイアウト、主要な画面設計:
同期的な意思決定(モブデザイン、デザインレビューなど)
細かいUIパーツの調整、インタラクション設計:
非同期的な意思決定(チャットスレッドでのフィードバック、コメントレビューなど)
機能改善、機能追加:
機能の方向性、優先順位決定:
同期的な意思決定(プロダクトオーナー、デザイナー、エンジニアなど関係者を集めた会議)
詳細な仕様検討、技術的な実現可能性検討:
非同期的な意思決定(チャットスレッドでの議論、ドキュメントでの情報共有)
緊急度の高い問題発生時 (クリティカルなバグ、サービス停止など):
状況把握、原因特定、対応策検討:
同期的な意思決定(緊急招集、関係者を集めたリアルタイム会議)
対応タスクの分担、進捗管理:
非同期的な意思決定(タスク管理ツール、チャットツールでの進捗報告)
初心者プロダクトデザイナーへのアドバイス
まずは両方のプロセスを経験してみる:
実際に同期的な意思決定と非同期的な意思決定の両方を経験し、それぞれのプロセスがどのようなものか、どのようなメリット・デメリットがあるのかを体感することが重要です。
状況に合わせて使い分ける意識を持つ:
プロジェクトの状況、チーム構成、課題の内容などによって、最適な意思決定プロセスは異なります。状況に合わせて柔軟に使い分ける意識を持ちましょう。
ツールの特性を理解する:
Slackなどのチャットツールは、非同期的なコミュニケーションに特化したツールです。ツールの特性を理解し、効果的に活用しましょう。
コミュニケーションの質を高める工夫をする:
非同期的なコミュニケーションでは、テキストベースでのやり取りが中心となるため、意図が正確に伝わるように、丁寧な言葉遣いや具体的な表現を心がけましょう。絵文字や画像などを活用することも有効です。
状況に応じてプロセスを組み合わせる:
同期的な意思決定と非同期的な意思決定は、排他的なものではありません。状況に応じて、両方のプロセスを組み合わせることも有効です。例えば、同期的な会議で方向性を決定した後、非同期的なSlackスレッドで詳細を詰める、といった使い方もできます。
まとめ
デジタルプロダクトデザインにおける意思決定プロセスとして、同期的な意思決定と非同期的な意思決定の2つのタイプを紹介しました。
同期的な意思決定は、迅速な意思決定やチームの一体感向上に貢献する一方で、時間や場所の制約などのリスクも抱えています。非同期的な意思決定は、時間や場所の柔軟性、記録の蓄積に優れる一方で、意思決定に時間がかかったり、コンテキストのずれが生じやすいというデメリットがあります。
それぞれの特徴を理解し、プロジェクトの状況やチームの特性に合わせて、最適な意思決定プロセスを選択、または組み合わせることが、質の高いプロダクトデザインを実現するための重要なポイントとなります。特に、初学者のプロダクトデザイナーの皆さんは、まず両方のプロセスを積極的に試し、経験を積むことから始めてみてはいかがでしょうか。