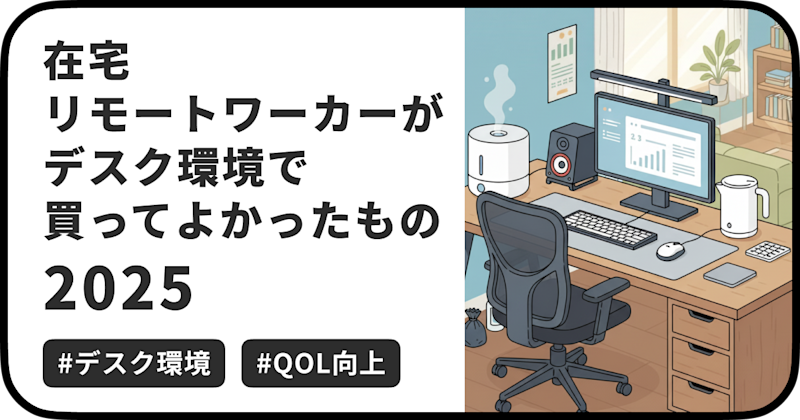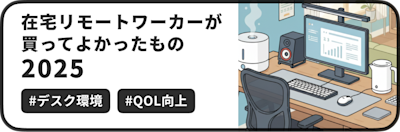他人のために働くのをやめよう
これは最近、私自身がマネジメントについて振り返るきっかけがあり、その際に自分が働く上での価値観を言語化したものです。
ふと、「これは、誰のための仕事だろうか」と思う瞬間があります。
「会社が」「組織が」と大きな主語で語りながら、「メンバーが」「彼らが」と個に寄り添ってばかりいると、「私(I)は」どうしたいのかという問いが、いつの間にか後回しになってしまうことがあります。
その葛藤こそ、自分が真摯にマネジメントに向き合っている証左と考えるようにしていますが、それでも、だんだん、自分は他人が輝ける環境を作ることが楽しいに違いない、とどこかで聞いたような綺麗事でしかマネジメントを語れない自分がいることに気づく瞬間があります。
私は本当に他人のために働いているのでしょうか?
「主語の多様化」の重要性
ところで、私が持っている仮説の一つに、メタ認知を極めた先にあるのは「主語の多様化」である、というものがあります。コミュニケーションの達人とは、話し手としても聞き手としても、一人称の「私(I)」、二人称の「あなた(you)」、そして三人称の「私たち(we)」という主語を自在に行き来できる人物に他ならない、というものです。
私は長年オンラインRPGをやっていましたが、優秀なパーティーを率いるリーダーの振る舞いからも感じるところがあります。自分一人の手柄ではなく、仲間がどうすれば役に立てるか(you)。そして、パーティー全体でどうすれば高難易度のクエストを攻略できるか(we)。コミュニケーションの達人は、その視点のトランジションを意識させずに仲間の視点を(I)から(we)へシームレスに転換し、結果として所属意識を高めたり、チームとしての一体感を醸成するのが上手いのだと思うことがあります。
自分自身がメンターをしていた時もそうでした。「私がやりたいこと」ではなく、「あなたが楽しめること」を主語にして共に歩むことで、初心者は成長し、やがて「私たちで一緒に高難易度コンテンツに挑み、報酬を得る」という瞬間がやってきます。
この経験は、マネジメントの現場でも一種の成功体験となっていると思っています。育成プロジェクトにおいて、「私が教えたいこと」を一方的に押し付けるのではなく、「あなたが学びたいことは何か?」を主語に据え、個々の熟練度に合わせて研修内容を柔軟に調整したりしました。結果的には、メンバーの成長に少しは役立てられたかなと思っています。
他者視点の罠と「一人称」の重要性の再認識
しかし、この「主語の多様化」には注意すべき落とし穴があります。他者の視点に立つことに専心するあまり、自分自身の「私(I)」という主語を見失ってしまうリスクです。いつしか、「他者の喜び」こそが「自分の喜び」であると錯覚してしまうのです。
「組織のため」「メンバーのため」、その大義は尊いものです。しかし、その言葉を盾に、自分自身の情熱や意思を押し殺してしまう瞬間があると思います。 組織の中で一度『私』という主体が『私たち』にすり替わってしまうと、周りに合わせて様子を伺いながらその時々で都合の良い選択を繰り返し、成功体験の自己参照を繰り返すことで最終的に同調圧力を強化していく集団になっていくのだと思っています(極端)。
この流れに飲み込まれないためには、「私は、本当はどうしたいのか?」と自らに問い続ける内省こそが、多様な主語を使いこなす熟練者の一つの姿だと考えています。
私は本当はどうしたいのか?
私は、社会において自分自身の存在感を極限まで小さくしていたいと思っています。目立ちたくありませんし、いてもいなくても一緒と思われていたいです。しなくても良いコミュニケーションをさせられるほど苦痛なことはありません。
なぜなら、私自身は他人に心底興味がありませんし、ゲームをするのも、仕事をするのも、全て自分のためにやっています。自分が豊かになって、その時に興味がある何かに飽きるまで打ち込み続けることがライフワークになっています。
しかしながら、自分が豊かになるには自分だけでできることは極めて少なく、社会と接点を持たなければ大したことはできません。なので、仕方なく社会と接点と持つわけなのですが、あまりにも非合理が多すぎるわけです。これでは、社会と接点と持ちたくない気持ちが強化される一方です。
なので、社会がよくなれば、私と社会の接点における摩擦を極限まで減らすことができ、社会の力を借りつつ自分のやりたいことに集中できるようになる可処分リソースが増えると考えています。つまり、自分のために社会をよくしてやろう、という考え方です。
たまたまそれを実現しようとしている組織の一つが今の会社であり、たまたまその中で私ができることと今の職能がマッチしており、たまたま需要があってマネジメントという業務をしているというだけです。育成に力を入れているのは、社会を良くできる人がもっと増えれば、あわよくば自分がやらなくても勝手に良くなっていくことを目論んでいるからです。できるなら全部他人に任せたい。他力本願。
人が働く理由なんてこれくらい自分勝手で良いと思っています。人のために働くのではなく、一人称の自分のために働きましょう。それがあなたのwell-workingになるのだと思います。