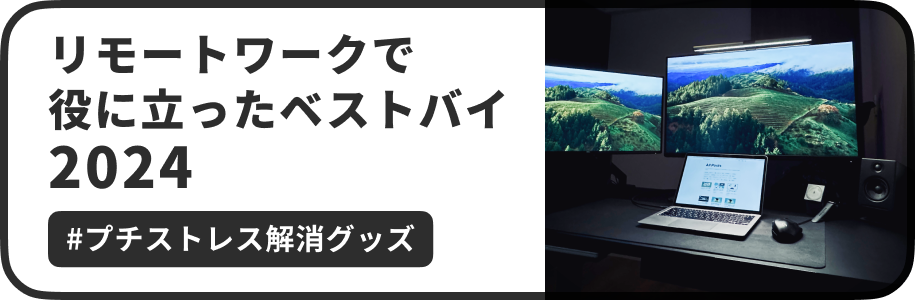なぜあなたのデザイン案は却下されるのか
自分では優れたデザインを提案できたを思っていても、それが受け入れられないという厳しい経験をした方は多いのではないでしょうか。技術的な能力やその評価は高くても、意思決定の場で発言力を持てないデザイナーは、自分のアイデアを実現できません。
この記事では、デザイナーが直面する「デザイン案が評価されない」という課題を乗り越えるための実践的なヒントを提供できればと思います。ここで紹介するコミュニケーション技術を習得することで、プロジェクトにおけるプレゼンス向上の足掛けになればと思います。
この記事の内容は次の順番で展開します。
意思決定の力学を知る
同期的コミュニケーションの作法
非同期コミュニケーションの作法
状況に応じた戦略選択
コミュニケーション能力がデザイナーの真価を決める
この記事のターゲット
技術的なデザインスキルはあるが、組織内での提案採用に苦戦しているデザイナー
意思決定プロセスでの発言力を高めたい方
同期・非同期のコミュニケーション環境で効果的に自分の意見を主張する方法を模索している方
1. 意思決定の力学を知る
デザインの成否はコミュニケーションで決まる
優れたデザイナーと偉大なデザイナーの違いは、しばしばコミュニケーション能力にあります。実のところ、デザイナーのスキルセットの中で最も洗練すべきは、Figmaの使い方ではなく、意思決定者を説得する能力と言っても過言ではないと思っています。
デザイナーが直面する2つの戦場
同期的コミュニケーションの戦場
リアルタイムの会議やモブデザインセッションで行われる即時的な意思決定
言語的・非言語的要素が絡み合う複雑な環境
発言力と存在感が成否を分ける
非同期的コミュニケーションの戦場
Slackスレッドやコメントで行われる時間差のある意思決定
文章力と論理構成が最大の武器となる環境
忍耐と継続的なフォローアップが必要な長期戦
同期・非同期コミュニケーションの具体については以下の記事でも説明していますので合わせて参考にしてください。
2. 同期的コミュニケーションの作法
会議前の準備
勝負は、準備の徹底でほぼ決まります。一言で言うなら、意思決定者にとって判断に必要な情報が全て揃っているほど意思決定の難易度は下がります。逆に、判断に必要な情報が不十分な場合、多くは紛糾するでしょう。
準備が十分にできていると、参加者にあらかじめ事前に情報を提供して前提を伝えやすくなり、会議の前に非同期的にキャッチアップを進めることで、会議中に資料を読み込んだりする時間を圧縮できるため、より円滑に意思決定できるようになる場合も多いです。
やるべきこと
会議の真の目的を見極める:単なる情報共有か、意思決定か、ブレストか
意思決定者を特定し、その人の関心事と決定基準を事前に調査する
想定される反論や反駁に対する対応策を用意する
複数のパターンや選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを準備する
視覚的資料(UIモック、プロトタイプ、ワイヤーフレーム)を用意し、実際の操作感を視覚的に伝えられるようにする
やるべきでないこと
何を決めたいのか不明確なまま会議に臨む
単一の案だけを用意する
デザインの専門用語だけで説明を構成する(意思決定者に伝わらない言葉を使う)
ビジネス目標やアウトカムとの関連性を無視する
会議中の戦略
参加者に会議のゴールを説明し、同意を得た上で自分の主張を伝えることがスタートラインになります。これによって、自身のスタンスを明確にすることで結果的に会議でのプレゼンス(存在感)が上がります。
その上で、ゴールに向かって話題が外れたら本筋に戻したり、発言が声の大きい参加者に偏っているようであれば、発言していない参加者に発言を促したり、その場における参加者の参加増幅を促すようなファシリテーションが必要になります。ここをおろそかにすると、話が発散して収束できなくなったり、声の大きい参加者に場を支配されてしまうなどの事態に陥りやすいです。
また、所属する組織や役割によっては、立場上批判的なスタンスで参加する(せざるを得ない)メンバーもいます。こうしたメンバーからの意見や批判も選択肢の一つとして受け入れた上で、建設的な反駁を行うべきです。ここで発言を拒否したり、相手を尊重しない態度をとるなど不適切な対応をとってしまうと、関係性を悪化させて最悪の場合対立構造に発展してしまい、そうなると今後に建設的な議論を展開することが難しくなりますので、公平に議題を取り扱う視点が重要になる場合もあります。
以下は、具体的に会議中に意識して取り組むべきことの例です。
やるべきこと
最初の5分で結論と理由を簡潔に述べる
ユーザーの視点とビジネス目標の両方からデザインを説明する
データや事実を用いてデザインの妥当性を裏付ける
一方的に説明するのではなく、参加者と対話し、意思決定に必要な条件を引き出す
質問に対して具体的かつ簡潔に回答する
議論を文書化し、決定事項を明確にする(後で見返せるようにする)
やるべきでないこと
デザインプロセスから説明を始める
専門用語を多用して聞き手を混乱させる
批判に感情的に反応する
他の提案を完全に否定する
議論を独占する
会議後の展開
会議で無事に意思決定や合意形成をした後、油断して何もしていないでいると、「あの時の会議の結果ってどうなったっけ?」だったり、「この観点での議論があまりできてなかった気がする」など、意思決定の結果が覆ってしまいもう一度会議を設定する羽目になるなど、ろくな目に遭いません。なぜなら、人は忘れてしまうからです。
人に忘れないようにさせるのは不可能です。必ず忘れます。「覚えていない方が悪い」は通じません。従って、忘れても大丈夫なように記録に残し、有意義な意思決定であったことを伝えるフォローアップが重要です。
これができるのとできないのとでは、社内で獲得できる信頼は雲泥の差になります。
やるべきこと
会議での決定事項と次のステップを文書化して共有する
決定に至った背景や理由を記録に残す
次のアクションと担当者、期限を明確にする
決定事項の実装状況を追跡する
やるべきでないこと
決定事項を曖昧なままにする
フォローアップを怠る
決定理由を記録しない
3. 非同期コミュニケーションの作法
非同期コミュニケーションの最も強力なところは、議論を可視化しながら構造的に情報を整理することができ、結論までの道筋をコントロールしやすいと言う点です。また、意思決定者と同期的な会議を設定するのが難しかったり、議論に必要なステークホルダの範囲が明確でない場合に、議論に巻き込みやすいと言う特徴があります。
ただし、議論に巻き込みやすいことはメリットだけでなく、デメリットにもなります。意図しない論点が生まれてしまったり、雪だるま式に参加者が増えていくと、互いの利害関係で折り合いがつきづらくなったり、結果的に雁字搦めになって意思決定ができなくなったりしていきます。いわゆる藪蛇です。
なので、同期的な場合と同様にゴールを伝えること以上に、いつまでに議論を着地するかの期限のコントロールも重要になってきます。
やるべきこと
目的と依頼事項を冒頭に明示する
段落や見出しを効果的に使い、スキャンしやすい構造にする
視覚資料(スクリーンショット、GIF、図表)を効果的に使用する
具体的な質問や選択肢を提示する
期限とアクションアイテムを明確にする
やるべきでないこと
長文で一気に情報を詰め込む
コンテキストなしに質問や依頼をする
抽象的な表現だけで終わらせる
フィードバックの方向性を示さない
非同期フィードバックの収集と活用
非同期環境でのフィードバック収集は、多くのデザイナーが苦手とする領域です。適切に設計されていないフィードバック依頼は、回答率の低さや的外れな意見につながりがちです。
効果的なフィードバック収集には「構造化」と「フォローアップ」が鍵となります。フィードバックを求める際は、単に「どう思いますか?」と尋ねるのではなく、具体的な質問や選択肢を用意することで、相手の思考の負荷を下げ、質の高い返答を引き出すことができます。
また、フィードバックを集めた後の対応もフィードバックそのものと同じくらい重要です。無視されたと感じたステークホルダーは、次回からの協力に消極的になるでしょう。
やるべきこと
フィードバックを求める目的と範囲を明確にする
具体的な質問を用意し、答えやすくする
フィードバックの期限を設定する
複数の選択肢を用意し、比較検討しやすくする
フィードバックに対して迅速に反応し、感謝の意を示す
やるべきでないこと
「何か意見はありますか?」という漠然とした質問だけで終わらせる
フィードバックを無視する
フィードバックの解釈を誤る
フィードバックへの対応を怠る
非同期での合意形成と意思決定
非同期での合意形成は、同期的な会議よりも時間がかかる場合が多いです。なぜなら、誰かが発言した後、その返信、返信、とキャッチボールをしていくことになりますので、合間に別の作業をしていたりするとリードタイムが長くなるためです。
その分じっくりと考え抜かれた結論に到達できる可能性があります。ここでの最大の課題は、議論が発散したり、途中で立ち消えになったりすることです。これを防ぐためには、定期的に議論の状況を整理し、進捗を可視化することが重要です。
また、意見の相違点だけでなく、共通点も明確にすることで、対立ではなく協力関係を育みます。議論が複雑化したり行き詰まりを感じたりした場合は、躊躇せずに同期的なミーティングに切り替えることも、優れたデザイナーの判断力の一つです。
やるべきこと
議論の現状と選択肢を定期的にまとめる
意見の分岐点を明確に示し、共通点を強調する
決定に向けた次のステップを提案する
最終決定と理由を文書化する
必要に応じて同期的な議論に切り替える
やるべきでないこと
議論を放置し、結論を曖昧にする
異なる意見を無視する
決定プロセスを不透明にする
複雑な問題を非同期だけで解決しようとする
4. 状況に応じた戦略選択
同期的アプローチが効果的な場面
同期的なコミュニケーションは、即時的なフィードバックやリアルタイムの反応が重要な場面で真価を発揮します。特に情緒的要素を含む議論や複雑な概念の説明には、表情や声のトーン、身振り手振りといった非言語的な要素が大きく貢献します。
また、多くの利害関係者間での迅速な合意形成が必要な場面では、全員が同じ時間と空間を共有することで、共通理解を築きやすくなります。重要な決断や方向性の転換など、プロジェクトの重要な局面では、参加者全員が「その場にいた」という共有体験を持つことで、後の実行段階での一体感も生まれやすくなります。
新規プロジェクトのキックオフ
方向性と基本方針の決定には、リアルタイムの対話が効果的
クリティカルな決定ポイント
多くの利害関係者が関わる重要な判断
複雑なデザインの説明
言葉だけでは伝わりにくい複雑なインタラクション
対立や意見の相違の解消
情緒的な要素を含む議論
緊急の問題解決
迅速な判断と行動が必要な状況
非同期アプローチが効果的な場面
非同期コミュニケーションは、じっくりと考え抜かれた返答や、個々人のスケジュールに合わせた参加が求められる場面で効果的です。特に細部の詰めや技術的な検討など、熟考を要する議論には、各自が自分のペースで考えられる非同期の環境が適しています。
また、グローバルチームや異なる業務スケジュールを持つメンバーとの協働では、時間的・地理的制約を超えて協力するための唯一の現実的な手段となることも少なくないでしょう。さらに、多数の選択肢から絞り込むような場面では、各オプションを視覚的に比較しながら検討できる非同期的なアプローチが効率的です。
詳細なデザイン仕様の策定
時間をかけて検討すべき細かな要素
多忙なステークホルダーからの承認
時間的制約のある関係者との協働
地理的に分散したチームとの協働
異なるタイムゾーンでの作業
深い思考と分析を要する問題
即時的な判断ではなく熟考が必要な課題
多数の選択肢からの絞り込み
比較検討が必要な場面
状況に応じてどちらも使い分けられるようになるべき
実際のプロジェクトでは、同期と非同期のアプローチを巧みに組み合わせることが最も効果的です。両方の長所を活かし、短所を補完するこのハイブリッドな戦略は、複雑なプロジェクトの様々な局面で応用できます。
例えば、プロジェクト開始時に同期的な会議で大枠の方向性を定め、その後非同期で詳細を詰めていくアプローチは、効率と質の両立を可能にします。あるいは、非同期で広く情報を収集した後、同期的な会議で最終決定を行うというパターンも効果的です。
ハイブリッドにコミュニケーションを設計することで、プロジェクト全体の進行をよりスムーズにし、質の高い成果物を生み出すことができるでしょう。
5. コミュニケーション能力がデザイナーの真価を決める
デザインスキルだけでは、アイデアを実現することはできません。同期と非同期、それぞれのコミュニケーション戦略を使いこなし、ステークホルダーを説得する能力こそが、真のデザイナーの価値を決定づけます。
デザインの質とコミュニケーションの質は比例します。この二つの能力を同時に高めることで、あなたは単なるピクセルを動かす人から、プロダクトの方向性を決定する影響力を持つデザイナーへのステップを登ることになるでしょう。
明日から実践できる5つの戦術
ここで紹介する5つの戦術は、特別な準備や環境がなくても、明日から即実践できるものです。これらはいずれも、デザイナーとしての技術的なスキルよりも、むしろコミュニケーションと説得の基本に関わるものです。
デザインの背景と理由を明確に語る能力は、単なる「見た目が良いから」という主観的な判断を超え、より説得力のある提案を行うための基盤となります。また、ユーザー視点とビジネス目標の両方から説明する習慣は、異なる立場のステークホルダーに対して共感を示し、信頼関係を構築する上で重要です。
デザインの背景と理由を明確に語れるようにする
「なぜ」この決定をしたのかを説明できるようにする
ユーザー視点とビジネス目標の両方から説明する習慣をつける
一方だけに偏らない
会議前に主要関係者と非公式に会話する
事前に懸念や反応を把握しておく
視覚的資料の作り方を工夫する
比較が容易で、選択肢が明確な資料を準備する
決定事項と次のステップを文書化する習慣をつける
説明責任と透明性を確保する
これらの戦術を日常的に実践することで、段階的に自分の影響力を高め、デザイン提案でプレゼンスを発揮し、デザイナーとしての市場価値を高めていってほしいと思います。